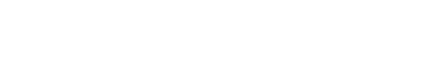御祈願
御祈願について
授与所
受付時間:9時 ~ 17時
御朱印
受付時間:9時 ~ 16時30分
諸祈願
受付時間:9時 ~ 16時30分
御初穂料
| 区分 | 御初穂料 |
|---|---|
| 個人様 | 8,000円~ |
| 企業団体様 | 15,000円~ |
| 七五三 | お子様お一人 5,000円 ※ご兄弟3人でお受けの場合、3人目のお子様は3,000円 |
本殿での撮影について
初宮詣・七五三等での同伴カメラマンによる本殿での撮影はお断りいたします。
※同伴カメラマンの方の車の乗り入れはお断りします。
祈願の種類
人生の節目・お祝い
- 厄除
- 帯祝
- 安産
- 初宮詣(お宮詣り)
- 誕生祭
- 祝寿
健康・安全
- 交通安全
- 心身健康
- 病気平癒
- 家内安全
- 除災招福
開運・願望成就
- 開運
- 心願成就
- えんむすび
商売・事業
- 商売繁盛
- 産業隆昌
- 安全
その他
お申し込み方法
- 御祈願は予約制ではございません。受付時間内でしたらいつでもお申し込みいただけます。
- 企業団体様の新年安全祈願祭は混雑が予想されるため、事前のご予約をお願いしております。
- 一週間、一ヶ月、一年間の連日特別祈願も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大祭・例大祭の期間は、諸祈願をお受けできない時間帯がございます。
詳しい時間については事前にお問い合わせください。
お受けできない期間
- 1月3日・2月節分・2月11日・2月17日・11月23日
- 7月中旬:祇園例大祭
- 春・秋のお彼岸(3月・9月)
- お盆期間(8月)
令和七年度の厄年
厄年とは昔から忌むべき年と言われています。
本厄である大厄を挟んで前の年と後の年を「前厄」「後厄」とし、三年間が厄年にあたります。
四年目を「お礼参り」といい、無事に厄があけたお礼と開運の意味があります。
女性の厄年
| 厄年 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
|---|---|---|---|---|
| 前厄 | H20年 18歳 | H6年 32歳 | H2年 36歳 | S41年 60歳 |
| 本厄 | H19年 19歳 | H5年 33歳 | S64年 37歳 | S40年 61歳 |
| 後厄 | H18年 20歳 | H4年 34歳 | S63年 38歳 | S39年 62歳 |
男性の厄年
| 厄年 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | H14年 24歳 | S60年 41歳 | S41年 60歳 |
| 本厄 | H13年 25歳 | S59年 42歳 | S40年 61歳 |
| 後厄 | H12年 26歳 | S58年 43歳 | S39年 62歳 |
※数え年で表記しています。(数え年は今年なる年齢に1足した年です。)
五ヶ月目の戌(いぬ)の日
戌の日とは、元気な子供をたくさん生み、お産が軽い犬にあやかったものです。
妊婦さんが帯を巻く、五ヶ月目のその日に無事に出産できるようにお祈りするのです。
当神社では、安産祈願も常にお受けしております。
祝帯もご用意しておりますが、ご自身が使いやすいものをお持ちいただいても結構です。
御祈願の際にお祓い致します。
令和七年度の戌の日
| 月 | 日付・曜日 |
|---|---|
| 1月 | 5日(日)・17日(金)・29日(水) |
| 2月 | 10日(月)・22日(土) |
| 3月 | 6日(木)・18日(火)・30日(日) |
| 4月 | 11日(金)・23日(水) |
| 5月 | 5日(月)・17日(土)・29日(木) |
| 6月 | 10日(火)・22日(日) |
| 7月 | 4日(金)・16日(水)・28日(月) |
| 8月 | 9日(土)・21日(木) |
| 9月 | 2日(火)・14日(日)・26日(金) |
| 10月 | 8日(水)・20日(月) |
| 11月 | 1日(土)・13日(木)・25日(火) |
| 12月 | 7日(日)・19日(金)・31日(水) |
初宮詣
お宮参りは男の子は生まれた日を含めて31日目、女の子は生まれた日を含めて33日目に参拝します。地方によっては「モモカマイリ」として100日目に参拝される場合もあります。
日にちは上記のようにいわれがありますが、一番大切なのは赤ちゃんと産後のお母様のお体です。赤ちゃんとお母様の具合と、天候の良し悪しなどを参考にどうぞ御参拝下さい。
境内に写真スタジオもございます。御衣裳もご用意出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
小倉北区城内2-2八坂神社内 詳細は、いけなが写真館までTEL093-591-3100
祝寿
| 名称 | 年齢 | 由来・説明 |
|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 暦の上で丁度自分の干支が還ってくることからこういわれる。 |
| 古希 | 70歳 | 唐の詩人杜甫の詠んだ「人生七十年古来稀なり」から由来しています。 |
| 喜寿 | 77歳 | 「喜」の草書体が七十七に見えるところから。昔は厄年の一つでもあった。 |
| 傘寿 | 80歳 | 「傘」の略字が八十にみえるところから。 |
| 米寿 | 88歳 | 「米」の字を分解をすると八十八になるところから。 |
| 卒寿 | 90歳 | 「卒」の通用異体字「卆」が「九十」と読まれるところから。 |
| 白寿 | 99歳 | 「白」の字は、百から一をとったものであるところから。 |
| 茶寿 | 108歳 | 「茶」の字の草冠を二十として、その下の部分のを米の字とし八十八、足して百八になるところから。 |
| 川寿 | 111歳 | 「川」の字を分解すると111となるところから。 |
| 頑寿 | 119歳 | 「頑」の字を分解すると元が二と八、頁が百と一と八、足して119になるところから。 |
| 昔寿 | 120歳 | 「昔」という字を分解すると、廿(にじゅう)と百、足して120になるところから。 |
| 珍寿 | 120歳以上 | 120歳以上は大変珍しいので以降は毎年珍寿の祝いとなる |
外祭
地鎮祭・竣工祭・上棟祭・水神上げ・事務所開き・開店・家祓い、神主がお伺いして祭典を致します。
随時承っておりますが、要予約制ですのでお電話にてお問い合せください。
お問い合せは 八坂神社社務所 tel.093-561-0753
小倉祇園 八坂神社 祖霊殿(納骨堂)
好立地・安全・安心
小倉の一等地「小倉城内」窓の外には、四季折々の景色が広がります。